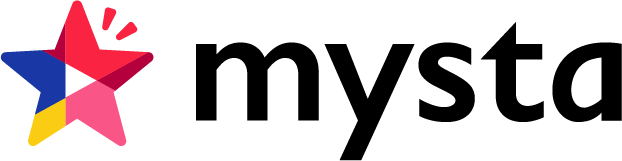イベント詳細
mysta新キャラクターの誕生を記念して特別イベントを開催!
日頃からmystaをご利用頂いている皆さんと一緒にmystaオリジナルキャラクターの名前を考えるイベント実施します!
もしかしたらあなたの考えた名前案が選ばれちゃうかも!?
名前の投稿は本イベントの動画コメント欄へ記入するだけ!
さらに考えたキャラクター名を記載した方の中からフリーコインGETのチャンスもあるよ!
※最優秀賞は該当者なし、キャラクター名が採用にならない場合がございます。予めご了承ください。
※本イベントはドリームイベントにて開催します。
※本イベントは有料&無料応援ポイントは関係ございません。
イベント実施スケジュール
2020年1月24日(金)12:30 ~ 2020年2月7日(金)12:29
特典
ユーザー特典
フリーコインプレゼント!
●キャラクター名採用!
最優秀賞:3,000フリーコイン
※該当者なしの場合あり
●mystaスタッフ選出!
グッドネーミング賞(MAX10名):300フリーコイン
【結果発表】
2月下旬ごろイベントページにて発表
注意事項
- 下記注意事項およびmysta利用規約、その他のルールを守って投稿しましょう。
- 本イベントへの動画投稿およびチアに際し、mysta利用規約の遵守をお願いいたします。
- 本イベントはmysta株式会社が主催しているものであり、アップル社、グーグル社によるものではありません。
- 自己アカウントおよび、自己アカウントに準じるアカウント(同じグループなど関係者含む)への応援はチア・ギフティング共に禁止とさせていただきます。
- 不正チア等の不正が発覚した際には、イベント終了後にランキングの修正を行う場合があります。
- 本イベントの投稿ルールまたはmysta利用規約への違反などにより動画投稿者本人がイベント参加資格を喪失した場合、賞金などのお支払いは致しかねます。
- イベント内容に記載されている事項を全て満たさずに動画を投稿した場合、mysta規約に違反した場合、またはmystaチームが不適切と判断した場合には、動画を差し戻しや非公開にする場合がございます。その際、イベント終了後であっても獲得ポイントは無効とし、特典の権利を無効とさせていただく可能性があります。
- 天災、不慮の事故などのやむを得ない事情により特典履行が行えない場合、特典が変更・補填・中止となることがございます。予めご了承ください。
- 万が一、前項に定める事由による特典履行が変更・中止となった場合、その他本イベントの応援ポイントが取り消しされた場合であっても、mysta株式会社は当該応援ポイントにかかるデジタルコンテンツまたはコイン、現金その他の返還はいたしません。予めご了承ください。